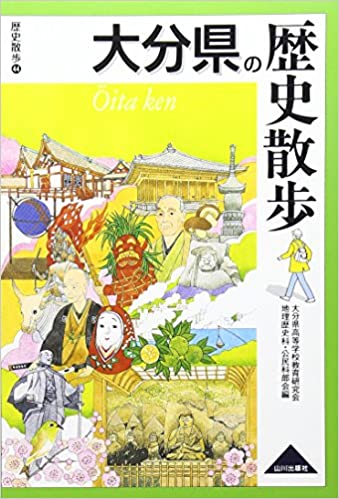大分・九州 観光 大分県の歴史散歩 歴史年表 Oita Kyusyu History |
|||||||||
|
|||||||||
| 時代 | 西暦 | 年号 | 事項 | 日本 | 外国 | ||||
| 旧石器時代 | 佐伯市聖獄洞穴、豊後大野市岩戸遺跡、大分市丹生遺跡、他 | ||||||||
| 縄文時代 | 早期 | 早水台(そうずだい)遺跡/日出町川崎、杵築市川原田洞穴、 枌洞穴(へぎどうけつ)/中津市本耶馬溪町、久重町二日市洞穴 |
|||||||
| 前期 | 国東市羽田遺跡、竹田市竜宮洞穴、大分市横尾貝塚 | ||||||||
| 中期 | 豊後高田市六所権現岩陰遺跡 | 約5000年前、火焔土器の出現 | |||||||
| 後期 | 大分市小池原貝塚、豊後高田市森貝塚、宇佐市立石貝塚、 豊後大野市夏足原遺跡 |
||||||||
| 晩期 | 豊後大野市大石遺跡、由布市下黒野遺跡 | ||||||||
| 弥生時代 | 前期 | 宇佐市東上田遺跡・台の原遺跡、日田市吹上遺跡、佐伯市白潟遺跡 | 紀元前5世紀、稲作の開始 | 79年ベスビオ火山 噴火ポンペイ埋没 (イタリア) |
|||||
| 中期 | 宇佐市野口遺跡・樋尻道遺跡、大分市雄城台遺跡 | ||||||||
| 後期 | 竹田市石井入口遺跡、宇佐市別府(びゆう)遺跡、国東市安国寺 集落遺跡、豊後大野市二本木遺跡、大分市守岡遺跡 |
239年頃、卑弥呼が魏に遣使 魏志倭人伝 邪馬台国 金印 |
|||||||
| 古墳時代 | 前期 | 日田市小迫辻原遺跡、国東市下原古墳、宇佐市赤塚古墳・免ヶ平 (めんがひら)古墳、杵築市小熊山古墳、宇佐市福勝寺古墳 |
300年頃、大規模古墳の出現 大仙陵古墳(現、仁徳天皇陵)等 |
||||||
| 中期 | 大分市亀塚古墳・築山古墳、臼杵市臼塚古墳・下山古墳、杵築市 御塔山古墳 |
||||||||
| 後期 | 日田市ガランドヤ古墳・穴観音古墳、大分市千代丸古墳、国東市 鬼塚古墳、別府市鬼の岩屋古墳 |
||||||||
| 飛鳥時代 | 552年 | 流鏑馬の起源、欽明天皇が国の内外の戦乱を治めるため、九州豊前の 宇佐の地において、神功皇后、応神天皇を祀り「天下平定、五穀豊穣」を 祈願し、最も騎射に長じた者を馬上から三つの的を射させた神事が始まり とされる。 |
|||||||
| 571年 | 宇佐神宮 ご示顕(じげん) 八幡大神(第15代応神天皇) 第29代欽明天皇の時代 |
593年聖徳太子、推古天皇の摂政 600年遣隋使派遣、小野妹子 |
|||||||
| 645年 | 大化元 | 羅漢寺、開基:法道仙人(インド) | 645年大化の改新 天智天皇(中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)即位 663年白村江の戦い(百済)、唐・ 新羅連合軍に敗れる 672年壬申の乱 天武天皇即位 694年藤原京に遷都 701年「大宝律令」完成 |
||||||
| 702年 | 大宝2 | 豊前国戸籍・豊後国戸籍が作成される。豊前仲津郡丁李里・ 上三毛郡塔里・加自久也里などの戸籍、正倉院に現存 |
|||||||
| 奈良時代 |
710年平城京に遷都 | ||||||||
| 718年 725年 733年 746年 749年 769年 784年 |
養老2 神亀2 天平 天平18 勝宝元 神護 景雲3 |
富貴寺(国宝、開基:仁聞 豊後高田市 重要文化財) 両子寺 開基:仁聞 国東市 宇佐八幡宮宇佐郡小倉山に御殿を造立、八幡神(応神天皇)を 祀る。総本宮、全国4万社余 宇佐神宮二之御殿 比売大神(ひめがみ)女神を祀る、 龍岩寺(りゅうがんじ)開山:行基(ぎょうき):宇佐市院内 八幡神入京 宇佐八幡神託事件 大宰主神習宣阿蘇麻呂、道鏡天位託宣を奏す。 これにより和気清麻呂道鏡掃除の神託を奏す。 長岡京遷都 |
752年東大寺大仏殿の完成 |
||||||
| 平安時代 |
794年平安京遷都(桓武天皇) | ||||||||
| 823年 |
弘仁14 | 宇佐神宮 三之御殿神功皇后(じんぐうこうごう)を祀る。 (応神天皇の御母) |
804年最澄、空海の入唐 866年応天門の変(藤原氏摂政政治 |
||||||
| 827年 | 天長4 | 延暦寺金亀和尚、宇佐八幡を勧請し、柞原(ゆすはら(油原) 八幡宮を建立。 |
860年宇佐神宮を勧請し清和天皇 京都岩清水八幡宮創建 919年大宰府天満宮創建 (福岡) 921年筥崎宮(はこざきぐう) 創建(福岡) |
||||||
| 867年 | 貞観9 | 鶴見山噴火、火男・火売(ほのおほのめ)神前に大般若経転読。 2神を従五位上、正五位下に叙す。 |
|||||||
| 940年 | 天慶3 | 平将門追討報賽(ほうさい)のため、八幡大菩薩に封戸(ふこ) 30戸を寄進する |
935年平将門の乱 1051年前九年の役 |
||||||
| 941年 | 天慶4 | 海賊追討使源経基、豊後佐伯院で海賊の頭目桑原生行を 捕らえる。 |
1063年京都岩清水八幡宮を勧請、 源頼義、鶴岡八幡宮(鎌倉)創建 1083年後三年の役 1156年保元の乱 1159年平治の乱 1173年親鸞聖、浄土真宗開祖 1180年10月6日頼朝、鎌倉へ入る 1181年1月15日平重衡(しげひら、 清盛五男)南都焼討(大仏殿焼失) |
||||||
| 1144年 | 天養元 | 宇佐公道(うさのきみみち)豊前、宇佐神宮の大宮司(だいぐうじ)となる | |||||||
| 1156年 | 保元元 | 宇佐宮造替により、九州各国に諸役が割り当てられる | |||||||
| 1159年 | 平治元 | 平氏政権により宇佐公道(うさのきんみち)を豊前守に補任する | |||||||
| 1183年 | 寿永2 | 平宗盛(三男、母時子・長男)、安徳天皇を奉じ大宰府に入る。 平氏、安徳天皇を奉じて宇佐宮に来る 緒方惟栄(これよし)・臼杵惟隆(これたか、緒方惟栄の兄)・日田永秀ら 平氏を大宰府より追う |
|||||||
| 1184年 | 元暦元 | 緒方惟栄ら、宇佐宮を焼討ちする | |||||||
| 1185年 | 文治元 | 緒方惟栄・臼杵惟高ら、源範頼に兵船82艘を提供し、源氏を豊後へ 渡す。後白河法皇、院庁下文で豊後住人らを賞す 緒方惟栄、岡城築く、源義経を先導して九州下向途中に難破する。 源頼朝、申請して豊後国など9カ国を関東御分国とする |
1185年:壇ノ浦の戦い :源頼朝、義経追法 :守護地頭を設置 |
||||||
| 鎌倉時代 |
1192年頼朝が征夷大将軍に就任 | ||||||||
| 1197年 | 建久8 | 「豊後国図田帳」を幕府に上申する | |||||||
| 1206年 | 建永元 | この頃、大友能直、養父仲原親能から所領所職を譲られたとされる | 1203年比企能員の変(鎌倉) 1219年源実朝暗殺(鎌倉) 1221年承久の乱(後鳥羽上皇) 1232年鎌倉幕府執権北条泰時、 御成敗式目(51ヵ条)制定 |
||||||
| 1242年 | 仁冶3 | 大友頼泰、「新御成敗状」28ヵ条を定める | |||||||
| 1271年 | 文永8 | 幕府、鎮西(西海道)に所領を有する御家人に、下向し守護の指揮に 従い異国防御にあたることを命じる |
|||||||
| 1274年 | 文永11 | 文永の役、蒙古襲来、少弐経資(しょうにつねすけ)、大友頼泰、諸志 を率い、筑前博多(現福岡県)で蒙古軍と戦う |
|||||||
| 1276年 | 建治2 | 一遍、大隅国から豊後国に入り、大友頼泰帰依する | |||||||
| 1278年 | 弘安 | 角牟礼城(つのむれじょう)、築城主:森朝通 | |||||||
| 1281年 | 弘安4 | 弘安の役、蒙古再来、日本軍石築地により敵の上陸を阻止する 蒙古軍、台風に覆滅し敗退 |
|||||||
| 1284年 | 弘安7 | 幕府、六郷山寺院に異国降伏の祈祷を命じる | |||||||
| 1285年 | 弘安8 | 大友頼泰、「豊後図田帳」を幕府に注進する | |||||||
| 1306年 | 徳冶元 | 大友貞親(さだちか)、万寿寺(大分市)を創建し、直翁智侃 (じきおうちかん)を開山とする |
|||||||
| 1333年 | 正慶2 | 大友貞宗、少弐貞経ら、後醍醐天皇に応じ、鎮西探題北条英時を 攻める |
1333年、鎌倉幕府滅亡、 建武の新政(後醍醐天皇) |
||||||
| 1334年 | 岡城改修・拡張:志賀貞朝(大友氏一族) | ||||||||
| 室町時代 (南北朝時代) |
1336年足利尊氏が建武式目を制定(南北朝時代:1336年~1392年、57年間) | ||||||||
| 1336年 | 建武3 | 大友軍、足利尊氏に従って九州に下る。尊氏、宇佐宮に幡を奉納する。 大友貞順、南朝軍に従い玖珠城に拠る。大友軍尊氏の命を受け玖珠 城を攻める。大友ら九州勢、足利尊氏に従い上京し、楠木正成らを討つ |
1336年湊川の戦い(後醍醐天皇、 新田義貞、楠木正成x足利尊氏、 直義兄弟、九州勢) |
||||||
| 1355年 | 文和4 | 懐良(かねよし)親王(後醍醐天皇皇子)、日田に入り、ついで玖珠、 由布、挟間(はさま)を経て豊後国府に入る。大友氏一時くだる。親王、 さらに速見郡大神(現、日出町)、豊前国宇佐、城井を経て博多に 攻め入る |
|||||||
| 1361年 | 康安元 | 九州探題斯波氏経(しばうじつね)、大友氏時に迎えられ、豊後府中に 下り、高崎山城へ入る |
|||||||
| 1371年 | 応安4 | 九州探題今川貞世(了俊)子義範、田原氏能に先導され、豊後国高崎山 城へ入る。この年から翌年1月2日にかけて100余度、南朝の菊池武光ら が高崎山城を攻める |
|||||||
| 室町時代 | 1392年足利義満(第3代将軍)南北朝統一 | ||||||||
| 1394年 | 明徳5 | 杵築城:木付頼直が築く | |||||||
| 1403年 | 応永10 | 大内盛見、豊前国守護職に補任される | |||||||
| 1416年 | 応永23 | 大友親著、豊後・筑後両守護職に補任される | |||||||
| 1423年 | 応永30 | 大内盛見、宇佐行幸会を復興 | |||||||
| 1432年 | 永享4 | 大友氏と大内氏の合戦始まる | |||||||
| 1435年 | 永享7 | 大友持直、守護職を没収しようとする幕府に対して、海部郡姫岳城に こもるが、翌年、幕府により落城 |
1467年応仁の乱~ | ||||||
| 1496年 | 明応5 | 大友正親、義石父子不和となり、義石病死により正親が筑前国立花 (福岡県)に逃れる途中、赤間関(山口県下関市)にて大内義興に捕ら えられ、自刃 |
|||||||
| 1534年 | 天文3 | 大友義鑑(よしあき)、速見郡勢場ヶ原(杵築市)で大内義隆の軍と戦う | |||||||
| 1550年 | 天文19 | 二階崩れの変。大友義鑑、家臣に襲われ府内館で死去、嫡子義鎮 (よししげ)、乱を平定し家督を嗣ぐ(大友氏第21代当主) |
1543年鉄砲伝来 1549年キリスト教伝来 |
1517年ドイツ ルターの宗教改革 |
|||||
| 1551年 | 天文20 | フランシスコ・ザビエル、山口から豊後に招聘。大友義鎮、布教を許可 | |||||||
| 1552年 | 天文21 | 大友晴英、大内氏家督を嗣ぎ、大内義長と改名する(周防・長門大内氏 第17代当主、義鎮の実弟) |
|||||||
| 1555年 | 弘冶元 | ルイス・アルメイダ、府内(大分市)に育児院を建てる | |||||||
| 1556年 | 弘冶2 | 小原鑑元(おばらあきもと)の乱おこり、大友義鎮、臼杵・丹生島 (うすき・にゅうじま)へ避難 |
|||||||
| 1562年 | 永禄5 | 大友義鎮、入道し宗麟(そうりん)と号す 臼杵城、築城主:大友宗麟 |
|||||||
| 1571年 | 元亀2 | 大友軍、赤間関で毛利軍と戦う | |||||||
| 安土桃山時代 |
1573年織田信長が15代将軍義昭を京都から追放、室町幕府滅亡。1576年織田信長安土城を築く | ||||||||
| 1578年 | 天正6 | 大友軍、日向に出兵し、土持親成を討つ。大友宗麟、カブラルから受洗し ドン・フランシスコと称す。大友軍、日向国高城(宮崎県木城町)で 島津軍と戦い敗北 |
|||||||
| 1580年 | 天正8 | 巡察師ヴァリニャーニ、臼杵にノビシヤド(修練院)を開設 | |||||||
| 1581年 | 天正9 | ヴァリニャーニ、府内にコレジオ(司祭、修道士育成のための高等教育 機関)開校 |
|||||||
| 1582年 | 天正10 | 伊東マンショら遣欧少年使節、長崎を出発 | 1582年本能寺の変、太閤検地 1583年羽柴秀吉、大阪城を築く |
||||||
| 1586年 | 天正14 | 大友宗麟、島津軍の侵攻に備えて上坂し、豊臣秀吉に援軍を求める 島津軍、日向国、肥後国から豊後国に攻め入る、戸次川(へつぎがわ) 合戦(大分市戸次・大野川)。大友義統(よしむね、第22代当主、宗麟 嫡男)ら大敗し、府内は蹂躙される |
|||||||
| 1587年 | 天正15 | 豊臣秀吉の本体が九州に入り、島津軍撤退する。大友宗麟、隠居先の 津久見にて死去する。黒田孝高(如水)、豊前国6郡を領す。宇佐、下毛 上毛の武士、連合し黒田氏に抗す。毛利勝信、豊前国2郡を領す |
|||||||
| 1588年 | 天正16 | 中津城築城主:黒田孝高(よしたか)(如水)通称:黒田官兵衛 | |||||||
| 1590年 | 天正18 | 黒田氏、この頃までに豊前国を平定する | |||||||
| 1591年 | 天正19 | 大友義統、「豊前国検地目録」を増田(ました)長盛(秀吉、五奉行)に 提出 |
秀吉朝鮮出兵 1592年文禄の役 |
||||||
| 1592年 | 文禄元 | 大友義統、朝鮮国出陣 | |||||||
| 1593年 | 文禄2 | 大友義統、文禄の役における失態を糾され改易。豊後国は豊臣秀吉の 蔵入地となる。宮部継潤(みやべけいじゅん) |
|||||||
| 1594年 | 文禄3 | 豊臣秀吉、豊後国を再分配、中川秀成に岡7万石、福原直高に臼杵6万石、 早川長敏に府内1万2000石、竹中重利に高田1万5000石、垣見一直に 富来(とみく、国東市)2万石、熊谷直陳に安岐1万5000石、宮木長次郎、 毛利高政らに日田、玖珠郡など分封 |
|||||||
| 1596年 | 慶長元 | 慶長豊後地震、別府湾、瓜生島(うりゅうじま、沖の浜が海中に没する | |||||||
| 1597年 | 慶長2 | 臼杵城主福原直高、大分、速見、玖珠郡など6万石が加増され、府内城 (荷揚城)構築にかかる。この年、太田一吉(おおたかずよし)、臼杵に 報ぜられ、領内を検地 |
1597年慶長の役 1598年秀吉死去 |
||||||
| 1600年 | 慶長5 | オランダ船リーフデ号、臼杵・佐志生(さしう)沖に漂着(3月16日)。 関が原の戦いおこり、大友義統は西軍につき、速見郡石垣原 (現、別府市)にて細川、黒田連合軍と戦い大敗。岡城主中川秀成、 臼杵城に太田一吉を攻め降す。徳川家康、中津城主黒田長政を 筑前52万石に、細川忠興を豊前35万9000石に、稲葉貞道を臼杵 5万石に封ず |
1600年(慶長5年9月15日) 関が原の戦い |
||||||
| 1601年 | 慶長6 | 日出城築城主:木下延俊 徳川家康、来島康親(くるしまやすちか、改名長親)を豊後森(玖珠町) に封ず。竹中重利、高田城より府内城2万石、預り地1万5000石に 封ぜられ、城下町を整備。毛利高政は日田郡の隈城より佐伯に、 木下延俊は日出に封ぜられる。この夏、肥後国の加藤清正、天草郡 の替地として、豊後国大分郡、海部(あまべ)郡、直入郡の一部を 与えられる |
1602年小倉城築城細川忠興 | ||||||
| 江戸時代 | 1603年徳川家康が征夷大将軍に任命 | 産業革命・ イギリス18世紀後半~ |
|||||||
| 東西本願寺別院(宇佐市四日市) | |||||||||
| 1578年 1600年 1623年 1637年 1744年 1748年 1825年 |
天正5 寛保4 延亭5 文政9 |
出家入道四日市領主渡邉加賀守 真勝寺道場統述 實相山真勝寺親鸞上人御影申し受け 真勝寺(別院)騒動寺社奉行大岡越前裁き 公儀召し上げ後、東派へ 下げ渡される 四日市御坊真勝寺本願寺兼帯所豊前四日市 浄土真宗本願寺派(西)正明寺移転建立 四日市別院浄土真宗大谷派(東) 九州御坊として本堂、伽藍の整備 |
|||||||
| 1614年 | 慶長19 | 豊後でキリシタンの迫害 | |||||||
| 1615年 | 元和元 | 国東郡出身のペトロ岐部カスイ、マカオへ渡航 | |||||||
| 1622年 | 元和8 | 細川忠利、豊後国、豊前国などの人畜改め(じんちくあらため、家数人馬数 の把握)を行う |
|||||||
| 1623年 | 元和9 | 幕府、越前北庄城主松平忠直(一伯)を改易し、豊後国萩原(現大分市)に 流し賄料5000石を宛行う |
|||||||
| 1632年 | 寛永9 | 細川忠利、肥後国54万石に封ぜられ、豊後国内にも領地を持つ 幕府、小笠原長次(ながつぐ)を豊前国中津藩8万石に、弟忠知(ただとも) を豊後国杵築藩4万石、松平重直を豊前国龍王(りゅうおう)藩(現宇佐市 安心院町、龍王城)3万7000石、1639年高田城に居城を移す(高田藩、 現、豊後高田市) |
|||||||
| 1634年 | 寛永11 | 幕府、日根野吉明(ひねのよしあき)を府内藩2万石に封ず | |||||||
| 1636年 | 寛永13 | 府内藩、柞原(ゆすはら)宮、放生会(ほうじょえ)に市を復興し、浜の市と 名ずける |
|||||||
| 1639年 | 寛永16 | 日田が、江戸幕府の直轄地天領(幕府領)となる | |||||||
| 1642年 | 寛永19 | 日出藩木下延俊の死去にともない、遺領2万5000石を長子俊治に、5000石 を次子延次に分与、立石領成立 |
|||||||
| 1645年 | 正保2 | 杵築藩小笠原忠知を三河(現、愛知県)に移し、高田藩松平英親を杵築藩に 封ず |
|||||||
| 1647年 | 正保4 | 岡藩、臼杵藩が絵図元となり、「豊後国国絵図」を作成 | |||||||
| 1650年 | 康安3 | 府内藩、初瀬井路(はつせいろ)を開く | |||||||
| 1656年 | 明暦2 | 府内藩主、日根野吉明(ひねのよしあき)死去、嗣子(しし、あととり)なく 封を没収される |
|||||||
| 1658年 | 万冶元 | 大分郡高松藩(現、大分市日岡)、松平忠昭、府内藩に封ぜられる | |||||||
| 1663年 | 寛文3 | 府内の商人、橋本五郎左衛門、七島蘭(しちとうい、畳表)移植に成功する | |||||||
| 1689年 | 元禄2 | 中津藩、荒瀬井路(本耶馬溪町樋田)完成する | |||||||
| 1694年 | 元禄7 | 貝原益軒(本草学者、儒学者)、史跡調査のため豊前、豊後を訪れる | |||||||
| 1700年 | 元禄13 | 豊前四日市陣屋設置、天領日田代官所管轄。 その後:豊前四日市陣屋跡地利用(宇佐市四日市)、1911年宇佐郡実科 高等女学校創立(明治44年)、1953年大分県立四日市高等学校改称 (昭和28年)、2007年大分県立宇佐高等学校統合(平成19年) |
|||||||
| 1735年 | 享保20 | 青の洞門、禅海和尚(ノミと鎚のみ、30年、手掘り | 1716年~享保の改革・徳川吉宗 | ||||||
| 1771年 | 明和8 | 中津藩医、前野良沢(蘭学者)ら、腑分け(解剖)を試みる | |||||||
| 1774年 | 安永3 | 解体新書(ターヘルアナトミア)刊行、前野良沢、杉田玄白、中川淳庵、 桂川甫周(ほしゅう) |
|||||||
| 1781年 | 天明元 | 佐伯藩毛利高標(たかすえ)、城内に佐伯文庫を開き、内外の書を収集 | |||||||
| 1783年 | 享和3 | 岡藩、田能村竹田、伊藤境河ら、唐橋(からはし)世済(君山)の遺志を 継ぎ、「豊後国志」を完成する |
|||||||
| 1807年 | 文化元 | 杵築藩領、両子手永の百姓、島原藩領(現豊後高田市)に逃散。 浅黄半襟逃散(あさぎはんえりちょうさん)一揆 |
|||||||
| 1807年 | 文化4 | 岡藩勝手方御用掛、横山甚助(じんすけ)、増徴、流通統制を目指し「新法」 実施。 |
|||||||
| 1810年 | 文化7 | 伊能忠敬ら、九州測量のため中津城下に到着 | |||||||
| 1811年 | 文化8 | 岡藩領直入郡四原(柏原、恵良原、葎原(むぐらばる)、菅生原)の農民蜂起し 横山甚助の「新法」廃止を要求。臼杵藩領に一揆波及 |
|||||||
| 1812年 | 文化9 | 一揆、豊後、豊前国内の延岡藩領、佐伯藩領、府内藩領、肥後藩領、 中津藩領、島原藩領と玖珠、速見、宇佐郡の幕府領にも広がる。岡藩、 横山甚助を罷免、そのほかにも「新法」加担者を処罰 |
|||||||
| 1817年 | 文化14 | 廣瀬淡窓、日田郡豆田町の桂林荘を堀田村(現日田市)に移転し、咸宜園 (かんぎえん)とする |
|||||||
| 1818年 | 文政元 | 杵築藩領の国東郡浦辺地方で打ちこわし発生 | |||||||
| 1823年 | 文政6 | 日田郡豆田町の豪商広瀬久兵衛、西国筋郡代(さいごくすじぐんだい)、 塩谷正義(しおのやまさよし)の命を受けて、小ヶ瀬井路(おがせいろ)を 完成 |
|||||||
| 1824年 | 文政7 | 塩谷正義、宇佐郡北鶴田新田の工事に着手 | |||||||
| 1831年 | 天保2 | 臼杵藩、藩政改革のため第11代藩主、稲葉雍通(いなばてるみち)の直書 を発表 |
|||||||
| 1832年 | 天保3 | 帆足万里(ほあしばんり)、日出藩家老に就任し、藩政改革に着手 | |||||||
| 1833年 | 天保4 | この冬、森藩、藩政改革に着手 | |||||||
| 1834年 | 天保5 | 中津藩、藩政改革に着手 | |||||||
| 1835年 | 天保6 | 帆足万里、家老職を辞し、日出の家塾で教授開始 | |||||||
| 1836年 | 福沢記念館、福沢諭吉旧居 | ||||||||
| 1838年 | 天保9 | 中津藩の黒沢庄右衛門、撫育会所(ぶいくかいしょ):藩の家中、町人の 負債救済機関)を創設。藩主第7代奥平昌猷(おくだいらまさみち) |
1841年天保の改革:老中水野忠邦 第11代将軍徳川家斉(いえなり) |
||||||
| 1842年 | 天保13 | 府内藩第8代藩主、隠居松平近訓(ちかくに)号は閑山、、藩政改革の号令 を発し、日田郡豆田町の豪商広瀬久兵衛を登用し、藩財政の収支を委ねる |
|||||||
| 1850年 | 嘉永3 | 豊後国北東部に大風雨 | |||||||
| 1853年 | 嘉永6 | 賀来惟熊(かくこれたけ)、島原藩領宇佐郡佐田村に(現、安心院町佐田) 大砲を鋳造。 「豊前羅漢寺下道」歌川広重六十余州名所図解(浮世絵版画) |
|||||||
| 1855年 | 安政2 | 賀来惟熊、島原藩領宇佐郡佐田村に反射炉を建設 | |||||||
| 1864年 | 元治元 | 長州藩攻撃のため、英米仏蘭の4ヵ国連合艦隊、姫島沖に集結する | |||||||
| 1866年 | 慶応2 | 杵築藩領で打ちこわし、一揆城下へ向かう | 1866年1月薩長同盟 | ||||||
| 1867年 | 慶応3 | 岡藩兵、朝廷の命により上京。臼杵藩主稲葉久通、病気のため名代の 上京を申請。以後、日出、中津、佐伯藩主が同様の願いをする。 10月14日大政奉還、第15代将軍徳川慶喜、12月9日王政復古の大号令、 明治天皇、第122代、父:孝明天皇 |
|||||||
| 明治時代 |
1868年(明治元年)1月3日~6日 鳥羽伏見の戦い 戊辰戦争 | ||||||||
| 1868年 | 明治元 | 佐田秀(さだひずる)ら、尊王攘夷派志士、長州藩浪士らと四日市陣屋、 東本願寺別院(宇佐市)を襲撃し御許山(おもとやま)に拠る(御許山騒動) 下毛、日田、玖珠郡の幕府領長崎裁判所管内に編入。松方正義、日田県 知事となる |
1868年五箇条の御誓文を発布 | ||||||
| 1869年 | 明治2 | 版籍奉還。各藩主、知藩事に任命される。日田、大野、直入、国東、宇佐郡 で農民騒擾(そうじょう) |
|||||||
| 1870年 | 明治3 | 日田、玖珠郡や庄内、別府、山香で農民蜂起 | |||||||
| 1871年 | 明治4 | 廃藩置県。中津、杵築、日出、府内、臼杵、佐伯、岡、森、日田県成立。 第一次府県統合により旧豊前国に小倉県(2町774村)、旧豊後国に 大分県(17町1801村)成立。初代大分県長官(参事、のちに県令)に 森下景端(かげなお、元岡山藩士)なる(赴任は1872年1月) |
|||||||
| 1872年 | 明治5 | 大区小区制施行、大分県は8大区159小区を設置。大分県で県中四郡一揆 (大分郡で勃発、海部、大野、直入の三郡に広がった農民一揆)おこる |
|||||||
| 1873年 | 明治6 | 玖珠郡で徴兵反対強訴(血税騒動) | |||||||
| 1875年 | 明治8 | 大分県で大規模な小区区画再編成(160小区、8町792村) | |||||||
| 1876年 | 明治9 | 小倉県を福岡県に編入。下毛、宇佐2郡は大分県に編入。「田舎新聞」創刊 | |||||||
| 1877年 | 明治10 | 西南戦争勃発(1月29日~9月24日)、増田栄太郎ら中津隊、薩摩郡に 呼応し、中津支庁、大分県庁を襲撃する。県北四郡一揆おこる。薩摩郡、 大分県に侵入。 大分に第二十三国立銀行開業 |
|||||||
| 1879年 | 明治12 | 県内でコレラ発生し、西日本一帯に広がる | |||||||
| 1880年 | 明治13 | 県立病院、県医学校開設 | |||||||
| 1885年 | 明治18 | 県立大分中学校(現、県立大分上野丘高校)設立 | |||||||
| 1889年 | 明治22 | 町村制施行。大分県は14町265村となる | |||||||
| 1893年 | 明治26 | 大分銀行営業開始 | |||||||
| 1900年 | 明治33 | 県立第一高等女学校(現、県立大分上野丘高校)設立。豊州電気鉄道 株式会社営業開始。別府、大分電車開通 |
|||||||
| 1901年 | 明治34 | 瀧廉太郎少年時代竹田で過ごし、岡城をイメージ作曲「荒城の月」 作詞:土井晩翠 |
|||||||
| 1912年 | 明治45 | 双葉山生誕 穐好定次生家 相撲資料館 横綱69連勝 | |||||||
| 大正時代 | 1912年明治45年7月30日明治天皇崩御、皇太子嘉仁(よしひと)親王が、大正天皇 (第123代)践祚(せんそ、即位) |
||||||||
| 1913年 | 大正2 | 大分紡績株式会社操業開始 | |||||||
| 1916年 | 大正5 | 日鉱製錬株式会社佐賀関製錬所操業開始 | |||||||
| 1918年 | 大正7 | 臼杵で米騒動発生 | |||||||
| 1919年 | 大正8 | 菊池寛「恩讐の彼方に」短編小説、中央公論 | |||||||
| 1922年 | 大正11 | 富士紡績株式会社、大分紡績株式会社合併 | |||||||
| 1923年 | 大正12 | 日豊本線全通 | |||||||
| 昭和時代 | 1926年(大正15年12月25日大正天皇崩御、皇太子裕仁(ひろひと)親王が、昭和天皇 (第124代)践祚(せんそ、即位) |
||||||||
| 1928年 | 昭和3 | 豊肥本線(熊本~大分)全通 | |||||||
| 1931年 | 昭和6 | 富士紡大分工場争議始まる | 1931年満州事変 1932年5・15事件犬養首相暗殺 |
||||||
| 1934年 | 昭和9 | 久大本線(久留米~大分)全通 | 1936年2・26事件高橋是清蔵相暗殺 | ||||||
| 1938年 | 昭和13 | 大分海軍航空隊開隊 | 第2次世界大戦(1939年~1945年) | ||||||
| 1939年 | 昭和14 | 宇佐海軍航空隊開隊(柳ヶ浦) | 1939年ノモンハン事件(満州、モンゴル)国境紛争 | ||||||
| 1941年 | 昭和16 | 大分放送局開局 | 1941年(昭和16年)12月8日 真珠湾攻撃、太平洋戦争突入 |
||||||
| 1942年 | 昭和17 | 豊州(ほうしゅう)新報と大分新聞社が合併し、大分合同新聞社となる | |||||||
| 1945年 | 昭和20 | 大分大空襲、大分市の中心街ほぼ焼失、第二次世界大戦終結(8月15日) | |||||||
| 1946年 | 昭和21 | 県、農地部を設置し、農地改革本格化 | |||||||
| 1947年 | 昭和22 | 細田徳寿(とくじ、茨城出身)、初の公選大分県知事に当選 | |||||||
| 1949年 | 昭和24 | 大分大学開学 | |||||||
| 1950年 | 昭和25 | 別府国際観光温泉文化都市建設法公布 | |||||||
| 1957年 | 昭和32 | 大分空港開港(1968年供用廃止)。アメリカ軍、別府キャンプの接収解除 | |||||||
| 1959年 | 昭和34 | NHK大分放送局開局。大分鶴崎臨海工業地帯1号地で建設起工式 | |||||||
| 1966年 | 昭和41 | 第21回国民体育大会(剛健国体)開催 | |||||||
| 1971年 | 昭和46 | 新大分空港(現、大分空港)開港。新日本製鉄大分製鉄所操業開始 | |||||||
| 1976年 | 昭和51 | 大分医科大学(現、大分大学医学部)開学 | |||||||
| 1979年 | 昭和54 | 県知事平松守彦、「一村一品運動」を初めて提起 | |||||||
| 1981年 | 昭和56 | 第1回大分国際車いすマラソン大会開催 | |||||||
| 平成時代 | 1989年1月7日(昭和64年)昭和天皇の崩御、皇太子明仁(あきひと)親王が第125代天皇に 即位。平成元年1月8日に昭和から平成へ改元 |
||||||||
| 1989年 | 平成元 | 大分自動車道、別府~湯布院間開通 | |||||||
| 1994年 | 平成6 | 宇佐別府道路全線開通 | 阪神淡路大震災1995年1月17日 午前:5時46分発生 |
||||||
| 1996年 | 平成8 | 大分自動車道全線開通 | |||||||
| 1998年 | 平成10 | 第13回国民文化祭・おおいた98開催 | |||||||
| 2002年 | 平成14 | ビッグアイ(現、大分銀行ドーム)でFIFAワールドカップの試合開催 | |||||||
| 2005年 | 平成17 | 「平成の市町村大合併」〔~2006年)で大分県は14市3町1村になる | |||||||
| 2006年 | 平成18 | 大分県のフラッグショップ「坐来大分」が、東京銀座にオープン | |||||||
| 2007年 | 平成19 | 県内初の県立中学校として、大分豊府中学校開校。別府市で、36ヵ国の 首脳・リーダーが参加して、第1回アジア・太平洋水サミット開催 |
|||||||
| 2008年 | 平成20 | 第63回国民体育大会(チャレンジ!おおいた国体)・第8回全国障害者 スポーツ大会(チャレンジ!おおいた大会)開催 |
東日本大震災2011年3月11日 午後:14時46分 |
||||||
| 2013年 | 平成25 | 国東半島宇佐地域が「世界農業遺産」に認定 二階堂正広、「恩讐の彼方に」漫画単行本発行、新潮社 |
|||||||
| 2015年 | 平成27 | 東九州自動車道県内全線開通 | |||||||
| 2016年 | 平成28 | 熊本地震発生(県内最大震度6弱)。日田祇園の曳山行事が「ユネスコ 無形文化遺産」に登録 |
|||||||
| 令和時代 | 2019年5月1日第125代天皇明仁が退位され上皇になり、明仁の第一皇男子である徳仁親王が 第126代天皇に即位(天皇の譲位に伴う改元) |
||||||||
| 2022年 | 令和4 | 大分県の歴史散歩・年表 HP掲載(2022年1月17日~随時更新) | |||||||
参考文献:大分県の歴史散歩、写真と絵でわかる「日本史」 etc.